ここから本文です。
令和7年度応急手当講習会予定表について
応急手当講習会について
普通救命講習1.・3.、上級救命講習を希望する方は事前学習として、Web講習「e-ラーニング」の受講を前提に実施いたします。
※e-ラーニング(Web講習説明のページ)
※普通救命講習1.・3.(普通救命講習編)上級救命講習(上級救命講習編)
不明な部分がございましたら下記「申し込み問い合わせ先」へご連絡ください。
定期講習会の開催については下記のとおり行います。
令和7年度応急手当講習会(予定表)(PDF:327KB)
(出前講習会につきましては、原則平日9時から17時までの間、10名以上の受講者に対し実施いたします。)
- 受付:受講申し込みは少なくとも、受講日1週間前までに電話でご連絡ください。
(受講人数に上限があります) - 対象者:うるま市内在住又は勤務者(それ以外の方は受講できません)
- 受講料:無料
- その他留意事項
- 講習会用資料は消防署で準備します。
- 受講修了者(普通救命講習1.・3.、上級救命講習)には、救命講習修了証を発行します。
- 受講申し込み時に1.お名前 2.性別 3.生年月日 4.住所 5.電話番号が必要となります。
(修了証交付のため) - 講習はハンカチ・マスクを持参し必要に応じ着用、軽装でお越しください
- 当日に37.5℃以上の発熱や体調不良を感じた場合、受講はご遠慮ください。
その際、消防本部警防課(975-2006)又は当日の会場消防署へ電話連絡をお願いします。 - 再講習については、3年ごとに受講してください。
申し込み問合せ先
- 具志川消防署 電話:(098)975-2001 FAX:(098)973-7505
- 石川消防署 電話:(098)965-0831 FAX:(098)965-0832
- 与勝消防署 電話:(098)978-3283 FAX:(098)978-2649
- 警防課 電話:(098)975-2006 FAX:(098)973-8313
応急手当講習会について
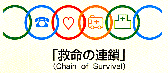 心臓が止まってしまうような重篤な状態の時には、応急手当はもちろん、救急車をすぐに呼ぶことや現場に居合わせた人による心肺蘇生(CPR)法、救急救命士による除細動(電気ショック)、救命救急センター等による高度な医療が、スムーズな連係プレーで行われることが救命のためには必要です。
心臓が止まってしまうような重篤な状態の時には、応急手当はもちろん、救急車をすぐに呼ぶことや現場に居合わせた人による心肺蘇生(CPR)法、救急救命士による除細動(電気ショック)、救命救急センター等による高度な医療が、スムーズな連係プレーで行われることが救命のためには必要です。
このことを救命の連鎖といいます。この連鎖が一つでも欠けたら命を助けることは出来ません。
当消防本部では、心肺蘇生法及びけがの応急的な手当の方法を習得してもらうため、市民の皆さんや事業所等を対象として応急手当の講習会を行っています。
近年、多種多様化する事故や災害等で、同時に多数の傷病者が発生したときは、身近にいる皆さんの自主的な救護活動が極めて重要となります。このようなときのためにも救命講習を受けましょう。
各種申込書等
- 救命講習等申込書(ワード:43KB)
- 応急手当指導員・普及員講習申込書(ワード:41KB)
- 認定証等再交付申請書(ワード:38KB)
- 救命講習用備品申込書(ワード:41KB)
- 救命講習用備品等損傷・亡失報告書(ワード:30KB)
講習の種類
| 種類 | 救急入門コース |
|---|---|
| 内容 | (1)短時間で成人に対する胸骨圧迫とAEDの使用が学べます。 |
| (2)応急手当ての入門編 | |
| 小学校高学年以上を対象に参加証を交付します。 | |
| 時間 | 90分 |
| 種類 | 普通救命講習1. |
|---|---|
| 内容 | (1)成人に対する心肺蘇生法 |
| (2)大出血時の止血法 | |
| (3)AED(自動体外式除細動器)の使用法 | |
| 時間 | 3時間 |
| 種類 | 普通救命講習3. |
|---|---|
| 内容 | (1)小児・乳児に対する心肺蘇生法 |
| (2)大出血時の止血法 | |
| (3)AED(自動体外式除細動器)の使用法 | |
| 小児・乳児に接する機会が多い方にお勧めしています。 | |
| 時間 | 3時間 |
| 種類 | 上級救命講習 |
|---|---|
| 内容 | (1)成人・小児・乳児に対する心肺蘇生法 |
| (2)大出血時の止血法 | |
| (3)AED(自動体外式除細動器)の使用法 | |
| (4)搬送方法 | |
| (5)外傷の手当方法 | |
| (6)傷病者管理方法 | |
| (7)副子固定 | |
| (8)知識の確認・実技の評価 | |
| 業務の内容等から一定頻度で心停止者に対し、応急の対応をすることが期待・想定される者。 | |
| 時間 | 8時間 |
| 種類 | その他(修了証の交付なし) |
|---|---|
| 内容 | (1)心肺蘇生法等を基本として、受講者の希望に合わせたコース |
| 時間 | 1~2時間 |
お問い合わせ先